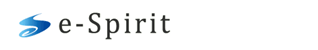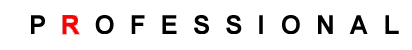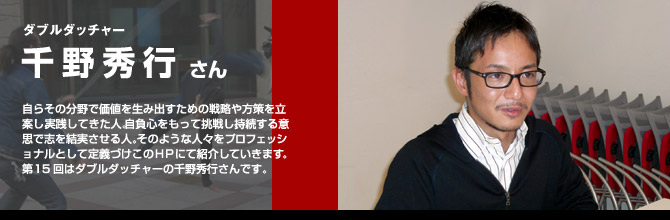
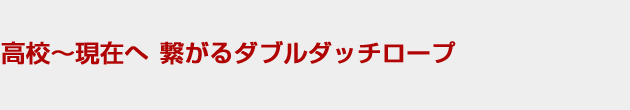

千野さんがダブルダッチを始められたのはいつ頃なんですか? 僕は渋谷の駒場学園って高校に入学して、渋谷で遊ぶ気満々だったんで特に部活なんてやる気もなかったんですけど(笑)、同じ中学の友達と一緒に部活紹介を見に行って、その友達と「ダブルダッチやろうよ」って。 高校の部活にダブルダッチがあったんですか? 同好会って形だったんですけど。 なるほど。 最初は自分の同学年が10人ぐらい入って、夏に先輩達にしごかれて何人かやめていって、最初に部活紹介を見に行った友達もやめちゃったんですけど(笑)。 ASGRM(所属チーム)は高校から現在まで繋がっているんですね。 そうですね。 縄を回す人(ターナー)、ジャンプする人(ジャンパー)の信頼関係は必要不可欠だと思うんですけど、そこは高校時代から続いている絆みたいなものが大きいんですかね? そうですね。信頼しあってやらないと、チームワークが一番大事なんで。 意見のぶつかり合いとかもあります? 殴り合いのケンカもあります(笑) 激しいですね(笑) はい(笑)。なんでしょうね。 |
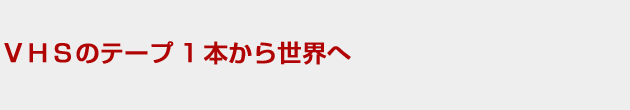
 |
そのチームがNDDL(国際ダブルダッチ連盟)世界大会で2連覇を成し遂げた訳ですが、会場があの有名なニューヨークのアポロシアターということで雰囲気はどうでしたか? 最初は変な日本人が来たよって扱いだったんですけど、パフォーマンスが始まったら全然、日本でショーをやるよりも100倍ぐらいボンって(反応が)きて、自分たちの音が聞こえなくなるぐらいの声援を受けて最後はスタンディングオペーションを頂いて。むちゃくちゃ気持ちよかったです。 |
|
そこまで受け入れられたのは何故だと思いますか? 僕ら高校から始めて、何を見て勉強したかって、黒人がダブルダッチをやっているVHSのテープ1本を見て勉強したんですよ。彼等がやってるダブルダッチって、音楽はかかってるんですけど、別にワンツースリーフォーのリズムで縄を回してないし、音楽は音楽でかかっていて、アクロバットをやったり、ステップを踏んだりって形で。 音楽は音楽で流れているものの、その音楽に合わせてパフォーマンスをするのではなく、部分部分で単純に技を見せていくだけという感じだったんですね。 僕らは周りにダンサーの友達が多かったんで、ダンスの音のとりかたっていうのを、まず学ばせてもらって、ロープもワンツースリーフォーで回せば、ジャンプもワンツースリーフォーで踊れるんだっていうことに気が付いたっていうか、そのやり方を見出して、それに黒人の好きなヒップホップをかけたりとか、ブレイクビーツ、ヨーロッパっぽい音楽を持ってったりとか、ハウスの音を持ってったりとかって、いろんな音で遊んでるうちに、なんとなく自分たちのスタイルってものができてきて、今は日本でも世界でも当たり前になってるんですけど、最初にそういうのを作ったっていうんですかね。 1本のVHSのテープから始まって、今では世界でも当たり前になっている、音楽と技を融合させたトータルなパフォーマンスとして見せていくスタイルを自分たちで作りあげたということですよね。海外でやられてきたなかで日本人の優れている点はどこら辺だと思いますか? うーん、音の使い方っていうのが海外のダッチャーに比べると、日本人は群を抜いてすごいのかなって。やっぱりバネとかバク宙の高さとかは黒人のほうがすごいんですよ。早く跳ぶのも。キレなんかは黒人はすごくあるので。それ以外の音の使い方、抜き方。黒人は抜くっていうことを全くしてこないですし。何でか分かんないですけど。そういうことは全然、日本人のほうが強いですね。 抜くっていうのは? なんて言うんですかね。パフォーマンスの中で、気合入れてキレを出してやるところもあれば、流しながら遊ぶみたいな雰囲気でガラッと変えたりとか。 なるほど緩急の部分、そこら辺が日本人の武器ということですね。 |
|
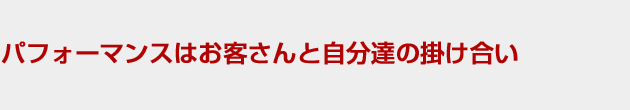

日本にダブルダッチが本格的に入って来て10年以上経って、世界大会でも日本のチームは良い成績を残しています。日本でもスポーツとして根付いてきている中で新しい世代に対してASGRMがこれだけは負けないってところはありますか? 自分がやってるパフォーマンスは映像でしか見れないんですけど。今の子達を見てても、なんだろうな。何が違うんだろう。全然違うんですよね。やっぱり今の子達って自分たちでやってるんですよね。パフォーマンスをやっちゃってる。ステージで「対客」じゃなくて、「対自分達」の成功率の問題であったり、引っ掛からないようにやったりとか、それに必死になっちゃって。 スポーツとしての技術は洗練されてきているものの、同時に何かが失われている? そうですね。僕らは多分、ショーの練習をしていて、最初から最後まで引っ掛からなかったことが11年やって多分、1回もないぐらいのノリなんですよ。でも本番のスイッチが入って音楽入れたら引っ掛からないでやる。学生達や下の子達を見ていると、練習でもほとんどノーミスで、80%ぐらい何回やってもノーミスだったのに、やっぱり本番は緊張して駄目だったねって。 ASGRMはお客さんに見せてなんぼという。 そうですね。すごいって言われるよりも、かっこいいと言われたい。そこの違いですよね。今の子達はすごいんですよ。僕らよりすごい。でも僕らのほうが絶対、かっこいいっていう自信はあるんですよね(笑)。 競技人口も増えて技術も伸びた。その次ですね。 そうです。だから今、どうすればいいんだろうと思って、ナイキさんと一緒にスリーオンスリーバトルっていうのを8月に1回目をやって、次に12月に2回目をやるんですけど。ダンスバトルってよくあるじゃないですか。あれのダブルダッチ版で、ダブルダッチってチームだいたい5〜6人でやってるんですけど、そういう枠も学生のうちからポンと外してもらって、違うチームのあいつがすごいと思った奴と3人で組んで、とことん3人でダブルダッチを追求してバトルするっていう。そのイベントで僕的には新しいダブルダッチが見えたんで、このままやり続けていれば何か変わってくるんじゃないのかなっていうのは感じましたけど。 従来の「チームありき」のダブルダッチの前提をとっぱらっちゃうと。 5人チームで、ほんとはチームのみんなでバク宙を合わせたいのに、1人できないからできないって悩みは、絶対に言葉にしちゃいけないんですけど、やっぱりチームでやってるからには心にあると思うんですよ。それをうまいこと壊してあげるというか、そういうイベントができたらと思ってやってるんですけど。 |
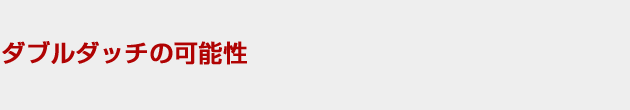

ダブルダッチがニューヨークでスポーツとして広められたのは若者の犯罪抑止という目的(※注)もあったそうですが、日本でも若者が夢を持てないとか言われてますけど、そこら辺の可能性はどうお考えですか? 僕もそうだったんですよ。渋谷で遊びたいから高校に入って、ダブルダッチは始めたんですけど、当時のギャル男っていうんですか?みんなでセンター街にたまってて。高1の冬ぐらいに、●●と●●が連合を組んで●●にケンカに行くって話になって。それは行かない奴は行かなくてもいいし、行く奴は気合を入れて来いよっていう感じで。 色々お話を伺ってきましたが、最後に千野さんにとってダブルダッチとは? 全てですよね。24時間それしか考えてないですし。パフォーマンスするもの、パフォーマーとしてのダブルダッチ。別の頭で、仕事としても、どうやって普及させていこうっていうダブルダッチ。ダブルダッチのことしかないんですよね。全てですよね、ほんとに。 ※1 1973年、NY市警の警官デビッド・ウォーカー氏が、ダブルダッチを楽しむ少女たちにヒントを得て、当時、社会問題化していた麻薬に手を染める若者たちの興味を引こうとルールを整備し、ダブルダッチがスポーツとして定着する礎を築いた。翌74年には、「第1回ダブルダッチ・トーナメント」が開催され、ダブルダッチは全米中に広まった。 |