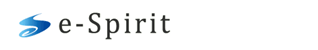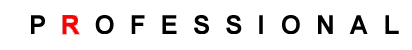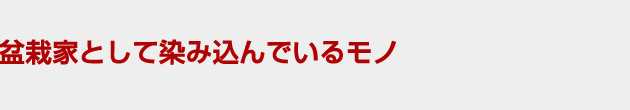

まず山田さんが盆栽家になられたきっかけをお聞かせください。 幼い時から、この仕事を継ぐのだと両親から刷り込まれていたのですが、 中学・高校の時は、友達に家業が「盆栽屋さんだよ」って言うのが恥ずかしくて、秘密にしていたぐらいでした。 大学も家業とは全く関係ない専攻でした。 ちなみに専攻は。 マーケティングでした(笑い)。 素敵ですね。 一番ビックリしたのがマティスのお墓に行った時に、たむけられていた大きい花輪でした。 具体的にどういうところにビックリされたのですか? ヨーロッパはリースの大きい花輪をあげるのですが、それがすごくセンスが良くて。
恐らく、その花輪はそのお墓の近辺なりの花屋さんが作られたと思うんですけど、
それを見た時にフランス人のセンスってこんな感じで行き届いているのだなって。 |
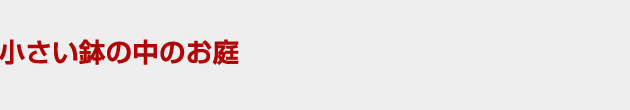
 |
だからってすぐに継ごうとは思わなかったんですけど。でもマーケティングの勉強したのが大きかったかなと思いますね。 もっと気軽に、カジュアルに楽しめる。 そうそう。盆栽をカジュアルに楽しめるナビゲーターがいないんだと思いました。
マーケティング的な発想ですよね。ニッチじゃないですけど。 |
|
やっている人がいないだけなのじゃないかって(笑い)。 盆栽の中に楽しみがあるというのは見て知っているので、盆栽のきれいな瞬間とか、素敵に思える瞬間とかも知ってはいたので。 紅葉もきれいだし。季節感もあるしとか。 どのような切り口で盆栽をカジュアルに楽しめるものしたのですか? 小さい鉢の中にお庭のようなものを盆栽で作ろうと思いました。盆栽は本来1鉢で山の景色を表現しています。でも抽象的すぎるし難しいと思われてしまう。 ミニチュアの世界観って素敵ですね。 そのためには、鉢ももっと可愛いものがなきゃいけないとか。 鉢の他に周辺ものってあるのですか? 例えばハサミもちょっと工夫して、女性でも「可愛い、このハサミ」って言ってもらえるような工夫をしています。 |


盆栽に関してのスタンスをお聞かせください。 私の場合、盆栽の技術は、一生勉強ってところがあるので、技術的な部分に関しては焦らず気長に構えようと最初に決めました。 具体的に技術は、どういうところが一番、難しいのですか? そうですね。重厚な本当の盆栽になってきますと、一枝を作り込むのに10年や15年計画になります。 想像するんですよね。 この枝はいらない。残す枝はこれとこれ、その枝を更に作っていくっていう。
全部、頭の中でシミュレーションしないといけないので。まず想像力が一つ。 完成した時は、ある程度の年数がたっているってことですね。 相手も生き物なんで、自分の思うとおりに成長してくれないってことも当然、ありますし。 最小限に残していたのに枯れちゃったとか。 盆栽家お父様から一番影響が受けたことをお聞かせください。 父の言葉ですごい、いいなと思ったのが「焦らず急げ」って言葉があるんですけれども。 難しいですよね(笑い)。 「焦る」というのは何をやるにしても、木作りにしても、精神的に負けちゃっている状態。 「急ぐ」のは積極的に活動していて、とてもポジティブなんですね。 深いですね。 焦って木をいじると、ほんとに木は枯れてしまいます。無理な施術をしてしまうということなんですけど。 木に対して、自分はこうしたいんだっていうのは、愛よりもエゴになっちゃうってことですね、多分。 木のエゴと人間のエゴのちょうど折り合ったところでやっているような仕事です。 |