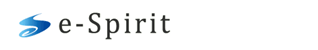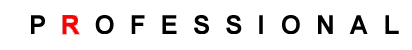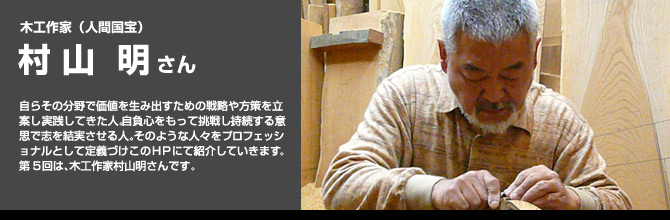

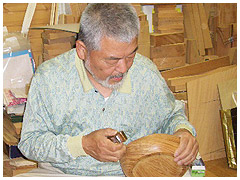
『つくる』ということに関しておききしたいのですが。 職人さんの場合やったら作る。僕らは創造の創で創るっていう言い方をするわな。
職人さんは「同じものをいかに手早くできるか」っていうことが仕事ってことになるわけや。それもどんどん変わっていって、
いろんな技術を身につけて、手仕事というようなことでやっている。 一番いい場所というのがあると。 そうそう。これやったら、ここで一個とかな。こういうふうに一個しかとれへん。 なるほどたとえば粘土だったら、同じ質感だから割り切ることができると。 そうそう。なんぼでも同じ。鉄でも同じやから。ただし、木は違う。 木目も違いますもんね。顔が違うってことですよね。 全部8個とれるかもわからない。6個かもわからないけどね。6個とれても1個も品物にならない。 ものとして。だってこれ3つとったら、確実に品物としてできる。 だから体積割り、面積割りしたってあかんわけや。絶対にな。 割り算じゃないと。 せやから量産にはある意味、向かへんな。今の時代。量産というのは木に対して実に失礼なやり方だと思う。
この木だとすごく長いこと生きている木。そんな木を勝手に人間の都合で邪魔になるからって切り倒して、
きれいな木が出そうやからって何百万もして売って、利益としてとって、僕らもその下のモノを買うてきて使うてるんやけんど、
実際、この木にとっては、そこにおったらもっとずっと死ぬまで長生きできるやんか(笑い)。
なんかのはずみで切られてかわいそうにって思う。
|
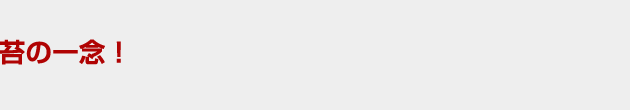
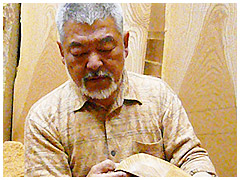 |
村山さんのお師匠さん、黒田辰秋さんのことをお聞きしたのですが?当時のエピソードとかあればお聞かせください。 僕らも最初、プロになるまで何させられた言うたら、1週間ビッタリ1日8時間ひたすら刃物を研いでいた。 8時間ずっと。 要は基礎やね。例えばカンナ研ぐ時、この通りスッと動く。手が決まんねん、これ。
砥石の上でな。これができなかったら仕事がでけへんのや。 良い仕事をするには何が必要なんでしょうか? |
|
苔の一念のように仕事をすることやな。 岩をも通すぐらいに。 もしほんとにその仕事をしたけりゃ、ずっと続けることも大事やろと思うわ。
仕事が忙しい、忙しい」って言うてる時は、実は忙しくない。本当に余裕がなくなったら、そんなこと言うてられへん。
そういう体験を実はもっとせなあかんと思う。6ヶ月徹夜続きとか。徹夜続きで、ただし時間があったら、
昼だろうと夜だろうと時間があったら寝れる時間に寝る。そういうことを3ヶ月や6ヶ月続ける。
自分の限界がどんなとこにあるのかという体験をしなくちゃいけない。
|
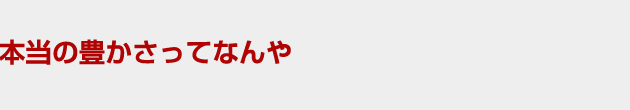

使う側の人が『気に入る』ということはどういうこのなんでしょうか? 人の気持ちの中でどのように生きていくかってことやな。創り手はそれを見越さないといけない。
一年経ったら、「こんなん、いやや。持ちたくないわ」ってものを作ってはいけないし。
それ素敵ですね。それは買った本人が気に入ってなきゃいけないっていうのと、 木自体も100年間もたなきゃいけないっていう。 意図的に嫌になられるってものは作らない。そういう意味ではできるだけおとなしいものが良い。 だけど創り手っていうのは、すけべ根性があるから、ついつい『何かしてみたい』という意図がでてしまう。 それをどう変化させていくかということを長いスパンの中で考えていかなきゃいけないな。 非常に奥深い見解ですね。 昔よりも明らかに生活様式が変わった。経済効率がいい生活様式に変わった。
人間同士が互いに疎外しあうという考え方は寂しいですね。 そやね。「お互い」ってことは、同じ権利を持っているということを認めないといけないということ。
自由であるっていうことも。実は息をすることでさえほんとは自由じゃないねんな。
お互いに空気の汚し合いしてんやから。自分一人で生きるんやない。いろんな人がいっぱいいて同じ権利を持って、
同じ喧嘩をしながら同じところにいるっていうことやな。
他人のために仕事をするってすごく難しいことだと思いますが? それのほうが本来、長続きする仕事やと思うな。自分は作るだけ。これを使ってくれる人があったら、
その人が喜んでくれるかどうかっていうことを先に考えたほうがいい。そうでないと仕事は常に変化を望むんだけど、
めまぐるしい変化になりすぎる。
限られたものでしょうね。原始人に近いというか。 そう。何かは創るかもしれない。土器とか武器とか。ただ今のように洗練されたもになるに時間がかかる。今あるものは過去の集積やからね。 |